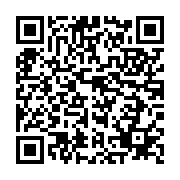深海魚の中でもかなり大型なウバザメが今月オーストラリア沖で捕獲された、というニュースがありました!
この海域でウバザメが捕獲されたのは約80年ぶりだそうです。
オーストラリアのビクトリア博物館によると、同国沖でウバザメが目撃されたのは過去160年間でわずか3回のみで、
最後に捕獲されたのは、1930年代のことだそうです。
今回捕獲された個体は、体長約6.3m。ウバザメは、ジンベイザメの次に大きなサメで、過去には
ノルウェーで12mという大きさのウバザメも捕獲されたことがあるようです。
日本でも過去に何頭か捕獲されているようですよ。
そのサイズとは異なり、性格はとても穏やかですが、餌であるプランクトンを食べる時には
その口を大きく開けて体の中の軟骨が丸見えな状態で捕食するので、さすがにその時の顔は
かなり怖く見えますよね(‘Д’)
世界中の海にいると考えられていますが、過去には乱獲をされて今は個体数が激減してしまったとか。
今回偶然にも捕獲されたのはとても貴重なことだったんですね。
海外ではダイバーにもとても人気があるというウバザメ、一度は見てみたいものです(^^♪
日付指定OW&AOW特割キャンペーン実施中!
https://sevenace.net/?page_id=14
海の日1泊2日 安良里・田子ツアー募集中!(7月18日19日)
https://sevenace.net/?page_id=14
大瀬崎花火ツアー 9月5日6日 募集中!
https://sevenace.net/?page_id=14
器材オーバーホールお得キャンペーン実施中!!
https://sevenace.net/?page_id=14